冬になると、毎年のように猛威をふるうインフルエンザ。特に職場・店舗・学校・クリニック・介護施設では、一度流行が始まると一気に広がってしまい、営業に支障が出たり、従業員の欠勤が増えて業務が回らなくなるケースも少なくありません。
実は、エアコンや換気システムの使い方を工夫するだけで、インフルエンザ感染リスクを大幅に減らすことができます。
この記事では、空調のプロが “実際に現場で効果があると感じている方法” を中心に、確実に役立つ対策を紹介します。
■ インフルエンザは「空気環境」で広がる
インフルエンザは、
・飛沫感染(くしゃみ、咳)
・接触感染
に加え、乾燥した空気で長く生存し、空気中で拡散しやすいという特徴があります。
冬に感染が増える理由は以下の通り。
- 室内の湿度が下がり、ウイルスが活性化
- 換気不足の空間に人が密集
- 暖房で空気が動かず、ウイルスが滞留
つまり、空調環境を整えること=インフルエンザ対策の第一歩なのです。
■ 1. 室内湿度を「40〜60%」に維持する
湿度が40%を下回るとウイルスが急激に生き残りやすくなります。
逆に、40〜60%をキープすると…
- ウイルスの生存率が下がる
- 喉や鼻の粘膜が乾燥しにくく防御機能が働く
「空調だけでは湿度管理が難しい」という場合は、
・加湿器の併用
・エアコンの加湿モード
が効果的です。
特に、業務用エアコン+加湿器の併用は、店舗やオフィスで最も取り入れやすい方法です。
■ 2. エアコンの「換気能力」を誤解しない
多くの人が間違えていますが、
ルームエアコンには “換気機能がありません”。
吸って → 冷やして/温めて → 吐き出す
だけなので、室内の空気が循環しているだけです。
換気として機能するのは、
- 換気扇
- 全熱交換換気(ロスナイなど)
- 換気機能付き業務用エアコン(モデルによる)
「窓を開けて換気」は寒いですが、
1時間に5〜10分で十分効果があります。
■ 3. CO₂濃度で換気不足をチェックする
換気ができていないと、人の呼気によってCO₂濃度が上がり、
1000ppmを超えると感染リスクが上昇するとされています。
最近は手軽なCO₂モニターが多数あり、
店舗・事務所・塾・クリニックなどで導入が増えています。
CO₂濃度が
- 800ppm以下:良好
- 1000ppm以上:換気不足
など、目安を見ながら換気タイミングを判断できます。
■ 4. 空調レイアウトを見直して空気の流れを改善
空気が滞留しやすい場所ほど、ウイルスも漂いやすい状態になります。
特に以下のような現場では要注意。
- 人が多く集まる受付付近
- 空調の風が届きにくい部屋の角
- 仕切り板が多いオフィス
- 天井高がある倉庫・大型店舗
改善方法としては、
✔ サーキュレーターで空気循環
✔ エアコンの風向を変更(水平吹き出しなど)
✔ 室内のレイアウト見直し
などが効果的です。
■ 5. フィルター清掃は「2週間に1回」が理想
フィルターが詰まっていると、
- 風量が落ちる
- 室内の空気循環が悪くなる
- 消費電力が20〜30%増える
という悪影響が出ます。
感染対策のためにも、
フィルター清掃は最低でも月1回、理想は2週間に1回。
業務用エアコンの場合、
グリス汚れ・タバコ・粉塵が多い環境では
プロによる洗浄を半年〜1年周期で行うと空気環境が改善されます。
■ 6. ウイルス対策に有効な「空気清浄機」を併用
近年は、
- HEPAフィルター
- プラズマクラスター
- ナノイー
- ストリーマ
など、空気中のウイルスや菌を抑制するモデルが増えています。
ポイントは、
部屋のサイズより少し大きめの能力(m³/h)を選ぶこと。
飲食店や待合室では特に効果が高いです。
■ 7. 定期的な空調点検で“冬の故障”を防止
インフルエンザ対策とは少し異なりますが、
冬にエアコンが故障すると換気も空気循環もできなくなり、感染リスクが跳ね上がります。
冬は結露・低温・霜取り運転などで負荷がかかりやすく、
予防のためには以下が重要です。
- ドレン詰まりの点検
- 送風ファンの汚れチェック
- ガス圧測定
- 室外機まわりの環境確認
特に、飲食店・クリニック・高齢者施設などは
冬前(11月まで)に点検するのが理想です。
■ まとめ|換気と空調を見直すだけでインフルエンザ対策は大きく変わる
冬のインフルエンザ対策は、
マスク・手洗いだけでは不十分です。
- 室内湿度40〜60%
- 換気は1時間に5〜10分
- CO₂濃度でチェック
- 空調レイアウト改善
- フィルター清掃
- 空気清浄機併用
- エアコン点検
これらを組み合わせることで、
職場・店舗全体の感染リスクを大幅に下げることができます。


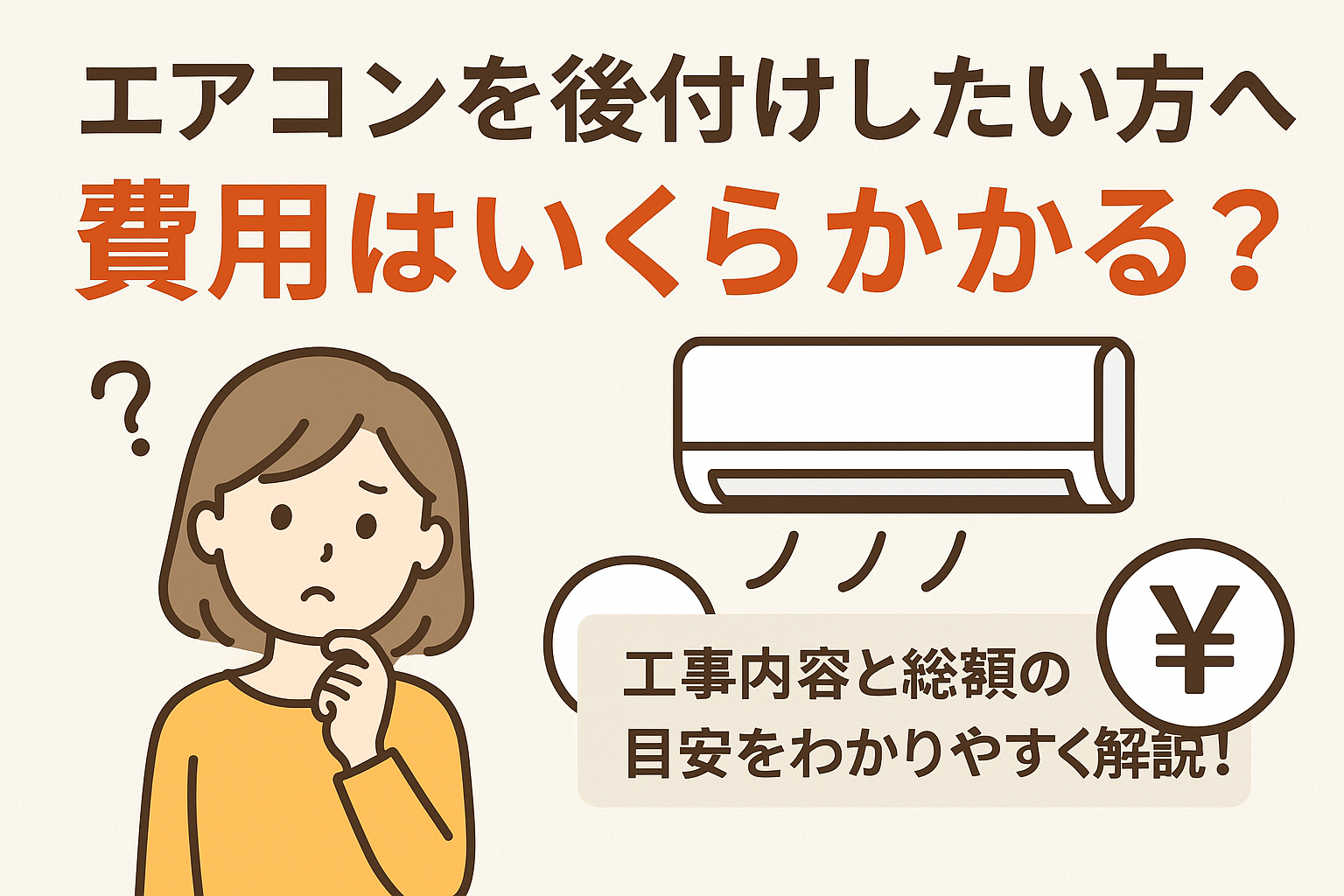
コメント