はじめに:空調設備が止まると、ビルは機能しなくなる
地震・台風・猛暑・大雨など、自然災害が増加する中で、
企業や施設運営者にとって「BCP(事業継続計画)」の重要性が高まっています。
とくに見落とされがちなのが、空調設備の停止リスク。
停電や機器故障によって空調が止まると、オフィスや医療施設、データセンターでは深刻な影響が出ます。
- 室温上昇による作業効率の低下
- サーバールームの過熱
- 高齢者施設や病院での健康被害
- 食品・製品の品質低下
これらを防ぐには、空調のBCP対策が欠かせません。
1. 空調が止まる原因とは?
災害時に空調が動かなくなる主な要因は、以下の3つです。
1️⃣ 停電(電源喪失)
空調機の多くは電力依存。非常用電源が限定的な場合、長時間の運転は困難です。
2️⃣ 室外機の損傷・浸水
台風・大雨で室外機が破損したり、基礎部分が冠水するケースが増加しています。
3️⃣ 冷媒漏れや機器故障
地震による振動で冷媒配管が破断し、再起動できない場合も。
これらは「自然災害による不可抗力」とされがちですが、事前準備と設備設計次第でリスクを最小化できます。
2. 災害に強い空調設計のポイント
✅ 非常用電源への接続
非常用発電機や蓄電システム(バッテリー)に、空調機の一部を優先接続することで、
最低限の空調(特にサーバールーム・医療機器室など)を確保可能です。
最近では、インバータ式の省電力空調機を選ぶことで、非常用電源でも運転できるケースが増えています。
✅ 室外機の設置位置と保護
室外機は浸水・飛来物の影響を受けやすい設備。
BCP対策としては、
- 高台・屋上への設置
- 防風パネルの設置
- 排水経路の確保
などが有効です。
これらの対策により、災害後の再稼働率が大きく向上します。
✅ 分散型システムの採用
一箇所の空調機に依存する集中型システムでは、
一部故障で全館が止まるリスクがあります。
近年では、ゾーンごとに独立稼働するマルチ型空調が主流。
停電・故障時でも、重要エリアのみを優先運転することが可能です。
3. 事業継続に向けた運用・管理の工夫
📋 定期点検と非常時マニュアルの整備
BCP対応では、「ハード(設備)」だけでなく「運用ルール」も重要です。
- 停電時の対応手順
- 再起動の注意事項
- 電源系統の確認フロー
- 点検履歴と予備部品の管理
これらをマニュアル化し、社内訓練で共有しておくことで、
いざという時に即対応できる組織体制を構築できます。
⚙️ 点検データのデジタル管理
点検記録をクラウドで管理することで、災害後の状況把握や復旧計画を迅速に進められます。
また、設備メーカー・施工業者・管理会社が情報を共有できれば、
修理や部品手配もスムーズに。
DX化されたメンテナンス体制は、BCP対策とも親和性が高いといえます。
4. 今後注目される「レジリエント空調」
“レジリエンス(resilience)”とは、「回復力・しなやかさ」を意味します。
空調分野でも、近年「レジリエント設計」という考え方が広がっています。
これは、
- 通常時は高効率・省エネ運転
- 非常時は最小限の電力で稼働可能
という二面性を持つシステム設計。
たとえば、ヒートポンプ式空調に太陽光+蓄電池を組み合わせることで、
電力網に依存せずに冷暖房を維持することが可能になります。
環境配慮と防災の両立を目指す上で、今後の主流となるでしょう。
5. まとめ:空調のBCPは“命を守るインフラ対策”
災害時の空調停止は、単なる「不便」ではなく、
人の健康・企業活動・設備資産に直結する重大リスクです。
- 停電対応の電源設計
- 室外機の耐災害対策
- ゾーン制御とマニュアル化
これらを組み合わせて、“止まらない空調”を設計・運用することがBCPの要となります。
🏢 URBAN空工の取り組み
URBAN空工では、
- 災害時の空調BCPコンサルティング
- 非常用電源対応エアコンの導入支援
- 室外機の高所・耐風施工
- 定期点検・復旧サポート
まで、一貫したサポートを提供しています。
企業・医療・公共施設など、止められない空調システムの設計・施工は、ぜひURBAN空工にご相談ください。
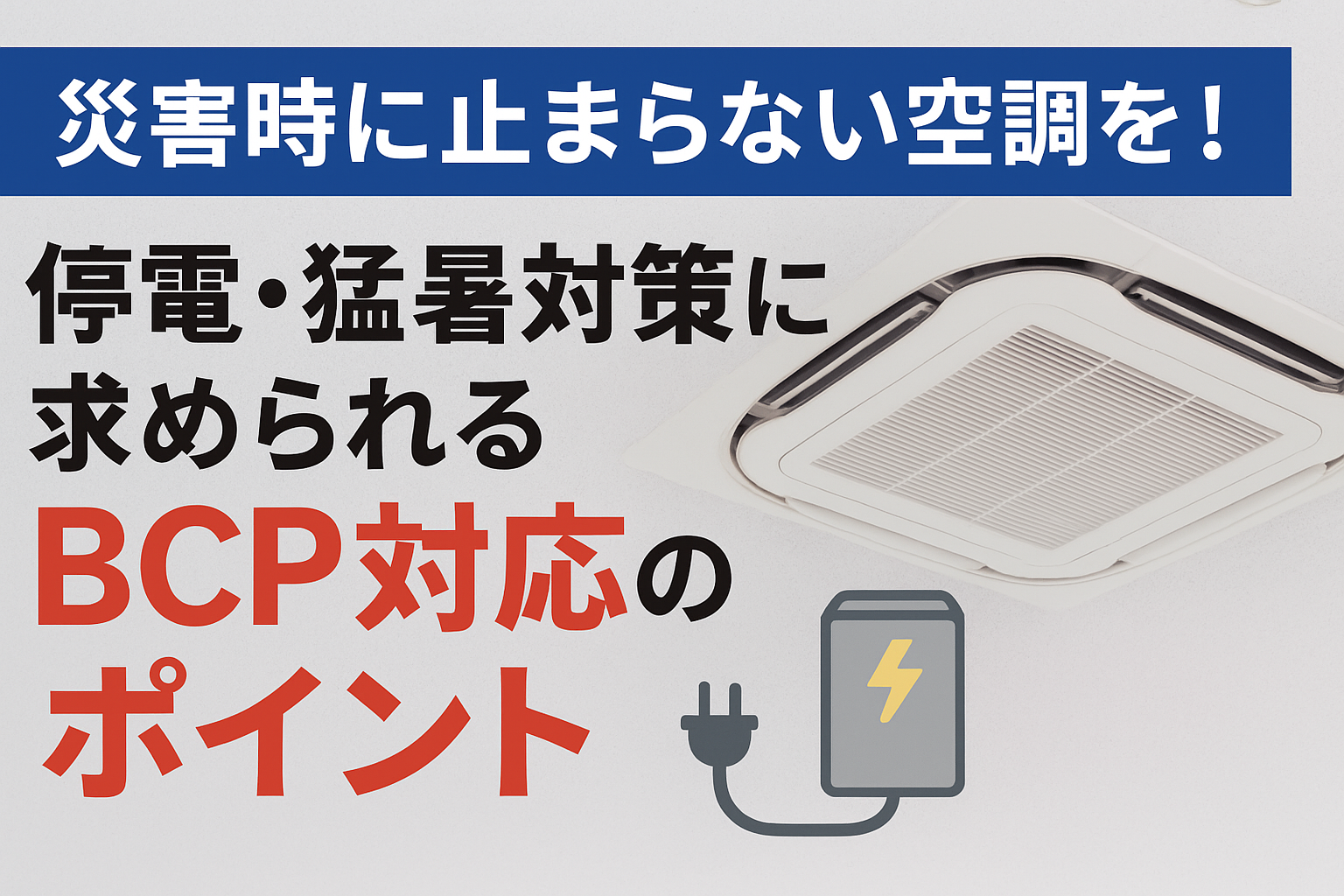
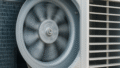
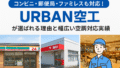
コメント